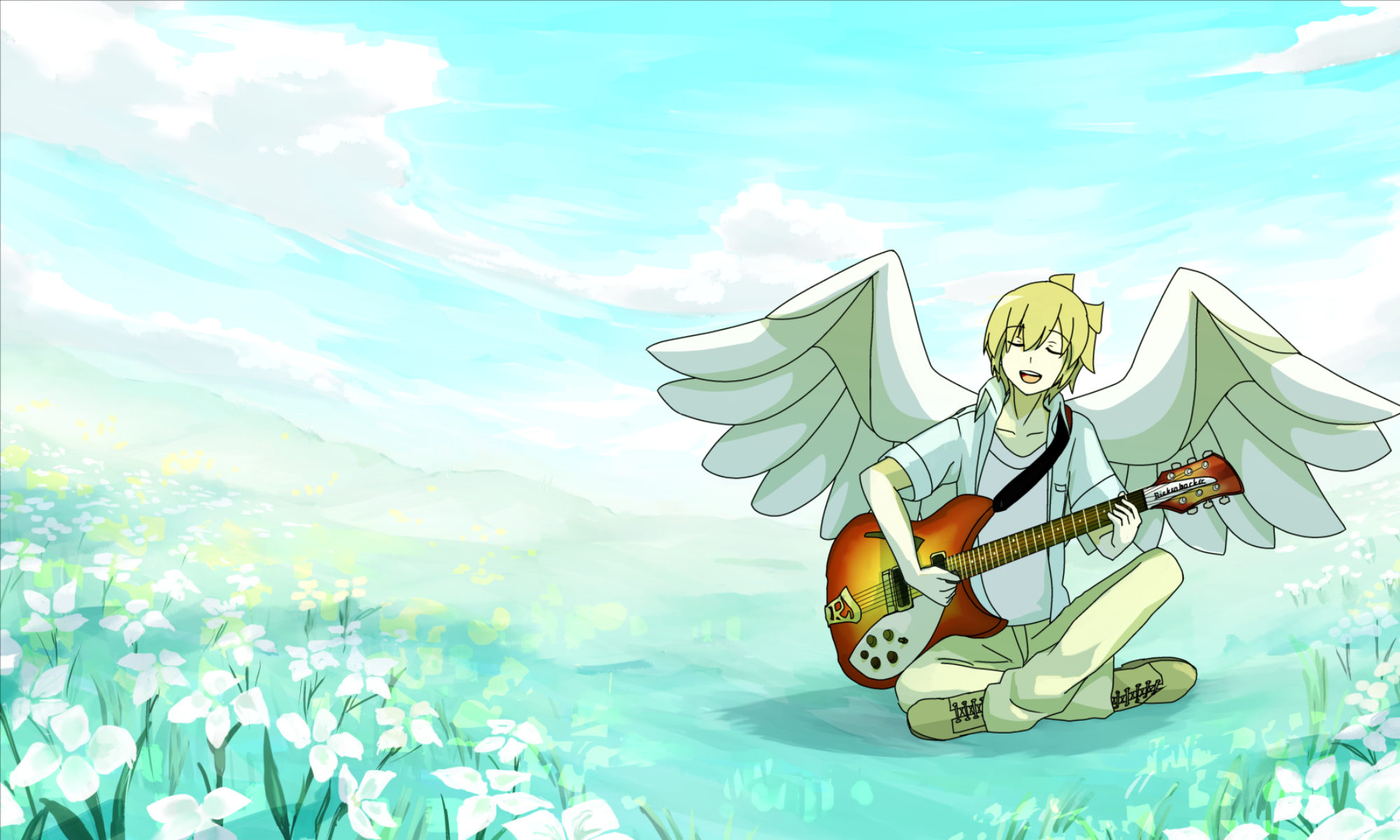8(11月下旬(23日~24日)のある晩)
夜のことである。杏子は、先刻(あるいは先日)ハル君から聞かされた、「自分たち以外のもともと人間だった使者たちの存在」について思い返していた。
彼らについて説明を求めると、開口頭、ハルは最初にこういった。
「まあ、防衛機構みたいなもんだよ」
「防衛、機構?」
この人は軽薄そうな見た目と裏腹に、時折、意味深な物言いをする、と杏子は思った。
「自分を殻の中に閉ざしてしまえば、外にどんなに酷い現実が繰り広げられていようとも、それ以上傷つかずに済むだろう?ってこと」
「それがあの姿とどう関係が?」
「苦しんでんだよ、あいつら」
説明する気があるのかないのか、ハルの物言いはどこまでも抽象的だった。
「嫌なことを見聞きしすぎると、少しずつ、身体やら羽根やらが外殻のように「あれ」で覆われていって、ああなっていくんだよな」
「え……?」
それだけ?と杏子は思った。私たちって、そういうものなの?
「すこしずつ、じわじわと」
「ねえ、それじゃまるで、私たちって、心がそのまま姿に反映されてしまうってこと?」
「うん、そう。適切に精神をたもってやらないと、それに応じて外見が変わり、……ある日、ドボンだ。もう、そこまで行くと戻ってこれない」
「……」
「大丈夫。もし杏子がそうなりそうになったら、俺が守ってやるから」
どことなく頼りないな。リップサービスだろうけど、と、杏子は思った。
杏子が、寝間着で建物の出入り口に立って消灯作業をしていたとき、ちょうどなにかの物を取りに来ていた曜子さんと出会った。
「あの、こんばんは」
「こんばんは」
普段はあまり私と関わろうとしてくれない曜子さんが、挨拶を返してくれた。
それだけのことなのに。
杏子は、今日は曜子さんは比較的機嫌がいいのかも、いま思い悩んでいることの相談に答えてくれるかも、と思い、思い切って聞いてみることにした。
「あの、今日ハル君からショッキングなことをきいたんです。きいてもいいですか」
「……ええ」
少し間があったようだが、答えてくれるようだ。きっと曜子さんは心根は優しい人だ、と杏子は思った。
「ハル君が言うには、私たち、使者は、精神を摩耗しすぎると、羽根や身体がこう、どんどん黒くなっていって……黒曜化、っていうんですか? 哀しい、寂しい、気持ちに蝕まれていってしまって、最後には悪魔のような姿になって、心も失ってしまう、って」
「ええ」曜子さんは肯定した。「そうよ」
当り前にそこにあることを当り前のように認める口調だった。たとえていうなら、目の前にマスキングテープがあって、これはテープですか?ガムテープのようなものですか?と聞かれて、「ええ、それと同じ。ただ少し弱いの」と答えるのと、声の音の感じとしては大差ない感じ。
杏子はその調子に驚いた。
「そう……なんですか」
「ええ。そうよ。ただし、正確には、心を喪うというよりは、閉ざしてしまうという方がニュアンス的に近いわ」
「失ってしまうわけじゃないんですね……」杏子は少しほっとした。ほんの少しだけだが。
「そうね。心の柔らかい部分はそのままに、哀しみのスパイスをふんだんにまぶしたまま狭い暗い心の奥底の蔵の中に閉じ込められるの。半永久的に。いえ、「存在している限り」永久的に、ね」
「……」
「『神様』、いえ、『上司』のずっと上の『上司』はどうしてこんな残酷なことをするんでしょうね。私たち人間には解らないわ。判りかねてしまうわ」曜子さんはそういって軽く笑った。乾いた笑いだった。
「彼らはどうなるんですか」杏子は半ばべそをかいていた。
「どうにもならないわ。ただ、表面的には業務を遂行する『上司』の忠実な従者と化して、そこに「在る」だけ。心の中は寂しさでいっぱい。この世のありとあらゆるものを恨み呪いながら、呪えば呪うほど、その状態の治癒からも、その境遇からの解放からも、遠ざかっていくのに、それでもやめられないの」
今日は饒舌になってしまってごめんなさいね。と曜子さんは言った。
「それならおとなしく死んだ方がましだったりしませんか?」
「ええ、そうね」
「河の向こうに、連れて行ってもらえないんですか」
「だって、彼らはそれを拒むのだもの」
「どうして?」
「……さあ?」曜子さんは首を傾げた。「もしかしたら『上司』も一枚噛んでいるのかもしれないわね」
「……」
「……もう、いいかしら?」
「あの、私、そういう風に、なりたくないです、だから、」
杏子は自分についていうのはちょっと我ままだとはわかっていた。でも、今の曜子さんなら聞いてくれるような気がした。
「どうしたら、そういう風にならないように……」
「私にそれ言う?」
曜子さんは薄くグレーの自分の羽の方を振り向いた。
「これよ」
「え?」
「私は彼みたいに強くないから。下界や周りの人たちからいろいろ影響を受けるわ。そして、いろいろ影響受けて心が「寂しくなった」結果がこれよ」
言われてみれば、ハル君と羽根の色が違う。
薄暗い闇の空の中でもわかる、白ではないグレーの羽根だ。盲点だった。
「……」杏子は絶句した。そして、俯く。
「曜子さんが、そんな状態だなんて、私、知りませんでした」
俯いたまま言う。
「ええ。だから私は他の人とは極力関わらないの。これ以上「寂しく」ならないために。寂しくならないために人に厳しくなるのね。
と曜子さんは言った。
「貴女もせいぜいそうならないように気をつけなさいね」
曜子さんはそう言って、自分が居城にしている建物に帰った。
なんでハル君は、夜はここにいないんだろう。肝心な時に頼りにならないな、と杏子は思った。