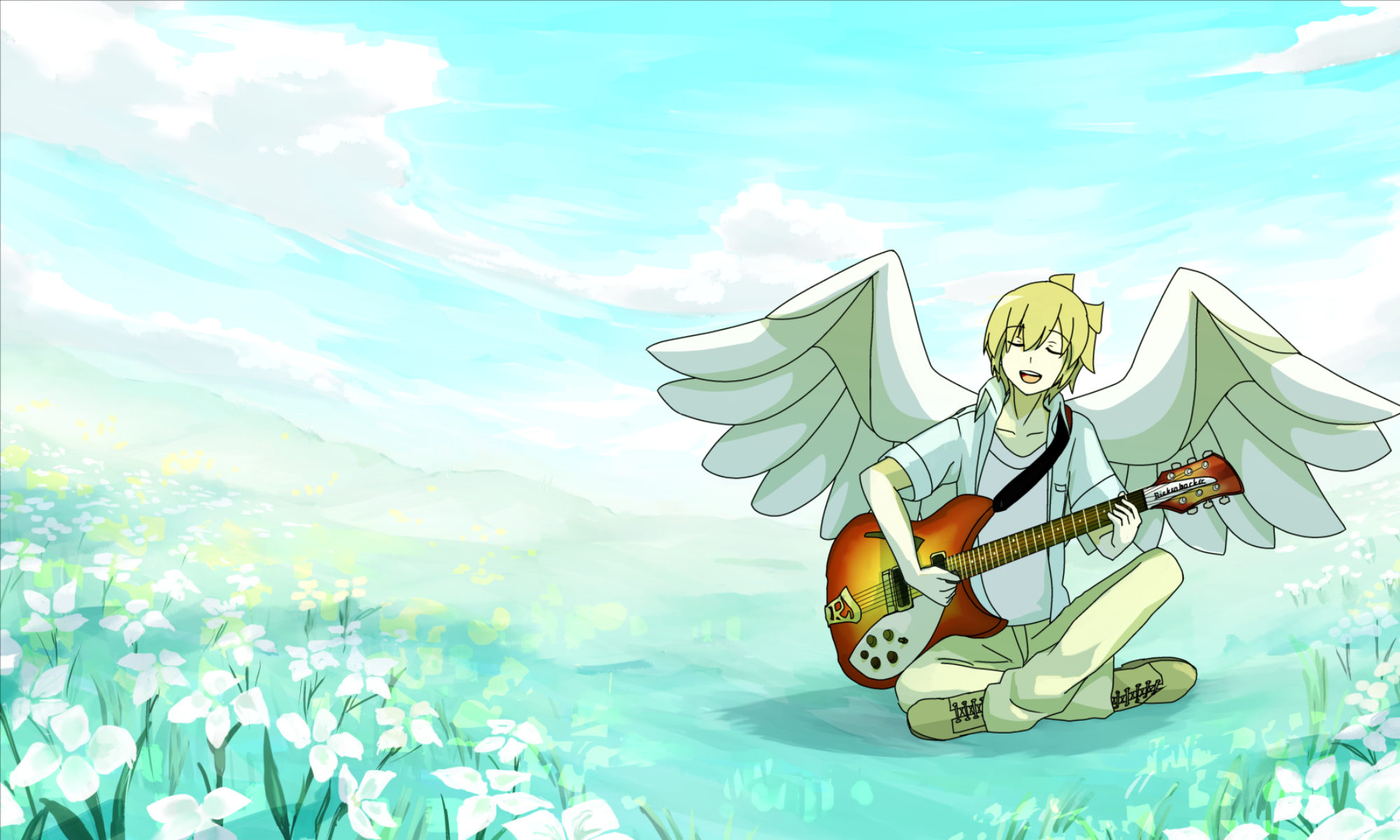7(11月24日)
使者について見に行く。
ーーー
杏子ちゃん 「そういえば、使者、二人しか居ないのは少なすぎませんか…?」
ハル「なので、多少時間を前後させたり…する権限も譲与されていたりする、わけさ」
杏子ちゃん「それで、足りるの?」
ハル「足りない」
杏子ちゃん「それでは…」
ハル「実は、二人きりじゃないんだ、本当は」
杏子ちゃん「!!!」
「この仕事をしている人は、本当はいっぱい居る、それも何十人もね、それでも単純計算では、数十人でこの仕事を回すには、ちょっと足りないぐらいなんだけど」「とはいっても、彼らは働き者だから」
「俺らは、こうやってのんべんだらりと、楽できるんだ」
杏子ちゃん「どういうこと?」
すると、ハルは説明を始めた。
「人間の魂は人間が、猫の魂は猫が、バッタの魂はバッタが…運ぶ、というのが「この世界の習わし」のようなんだけれども、
まあ、あちら『上司』様からしたら、ほんとうのところ人間の死者の魂を運ぶ仕事をする『機能を持った存在』が居ればいいわけで、それが俺らみたいに、人間らしい(人間としての自我を持った)、人間のままじゃないといけない理由はないわけなんだよな」
釈然としないままの杏子をよそに、ハルは続ける。
「だから、こちら『世界の狭間』の日本上空関東支部においては、俺ら人間らしい人間のままの人間、代表としては、俺と曜子さん、そしてこれからは、俺らプラス杏子ちゃん、の三人しか「残って」いないけれども、辛うじて人間の魂を運ぶ機能を残した人間のような何か、である『ひとたち』はいっぱい居るんだよな。そして、俺らじゃ回しきれない案件は『彼ら』がやってくれてる、いまでも」
杏子は、首をかしげた。ハルと曜子さんと、『上司』さん、以外の存在が世界の狭間にいる、と言われても、まだ見たことがない。
「よくわからないけれど、他に人が居る、っていうこと…?」
ハル「あいつらはこっち(の場所)が好きじゃないんだよ。(このあたりは)居心地が悪いらしい」
「……居心地、の問題?」
杏子は怪訝に感じた。世界の狭間は、穏やかで、凄く気候的にすごしやすい風土だった。
「それに」とハルがいった。「居たとしても、俺らに彼らは姿を見せたがらない。一瞬で消えてしまう、過ぎ去ってしまう。彼ら、俺らのそばにいたって、すぐに脇を通り抜けていく、風のように」「杏子もさ、周囲をすりぬけてく風みたいなの、感じたこと、なかった?」
「そういわれたら、あるかもしれない…」と、杏子は思った。
だろう?というふうに頷いて、
ハルは、すこし間をおいて口を開いた。
「悪魔ってしってるか」
「えっ、うん」唐突な問いに、杏子は少し戸惑った。
「まあ、宗教における悪魔みたいなもんだよ」と、ハルがいった。
「死後に天使が迎えに来るか、悪魔が迎えに来るか、で人生の決算が決まる、みたいなモチーフはどこの宗教でもあると思うけれど、それって、単に、その人の魂の運搬を担当した使者が、人間のままの姿の『俺ら』だったか、人間ならざる姿の『彼ら』だったか、の違い、にすぎないことなんだよな。こっちにきてから判ったけど、その人が生前犯した罪の重さとか、多分あんまり評価基準としては関係ないんじゃないかなぁ…と思ってる。あ、でも、俺も、『上司』がどんな判断基準で評価してるか、そういえば正確には知らないや…」
まるで御伽噺のようで、いまいちピンときていない様子の杏子をみて、
ハルは、杏子の目をみて、問いかける。「見にいってみるかい?」
杏子がうん、とうなずくと、ハルは、「世界の狭間」の奥のほうへ、普段見に行ったことのない領域へと、杏子を連れて行った。
そこは地獄の渓谷、といった雰囲気の光景だった。
ゴツゴツとした黒い岩肌の谷間のあちこちから、熱い蒸気が噴出し、そして、少し開けた場所には、この世ならざる白濁した熱湯が満ちていた。
杏子は一瞬、温泉のお湯の色が血の様な紅い色に見えたように感じてぞっとした。しかし、すぐに、その「紅」という印象をもたらした原因は、お湯の色自体ではなかったということに気付いた。
ハルに促がされ、杏子が渓谷へ近づくと、彼女が、「黒い岩肌」だとおもっていた幾つかが、無機物ではなく、動く生命体であることに気付いた。
どうやら、それは、人間ぐらいの大きさで、人間に近い形状をしているもののようだと気付いた。人間のように頭髪の生えた頭部があり、二本の腕があり、上半身がある。色は、真っ黒で、覗き込んだもの何もかもを飲み込むかのように黒い。そして、人間と異なる部分として、大きい一対の翼が生えていた。その翼も、また、黒かった。
驚いている様子の杏子を確かめてから、ハルがいった。
「彼らが、俺らの使者仲間さ」
杏子があまりのことに、ふらふらと茫然自失しないように、肩に手を置いている。
「働き者なんだよね。ていうか、「働く」ことしか、もう、表立った機能としては残っていないというか。」
杏子はちょっと状況が飲み込めなかった。つまり、死者の魂を誘う仕事を、あの黒い彼らが行っている、というのか。
ハルは言う。
「彼らねー。もう、楽しいとかあれやりたいとかこれやりたいとか、そういう人間的感情があまり残ってないんだよねー。だけど、「癒し」を求めるきもち、は辛うじて残っているようで、時間のあるときは、こうして、すこしでも癒し
を得ようとこういったところにじっとしていることが多いんだ」
杏子は、ハルのいいようが、飲み込めない。何か彼は重大なことをいい忘れているような気がする。
ハルは、杏子の怪訝なかおをみて、はたと何かに気付いたらしい。そして、付け足した。
「あ! そっかそっか…それすらわからないか」
「そうだよな、あれだけみたら、「根っからそういう風に生まれたそういう生き物」というふうに見えるよな」
ハルは、くすっとこらえるように笑った。いや、失礼かと思って、笑いをこらえたのかもしれない。
「彼ら、元は、俺らと同じ、人間なんだ」